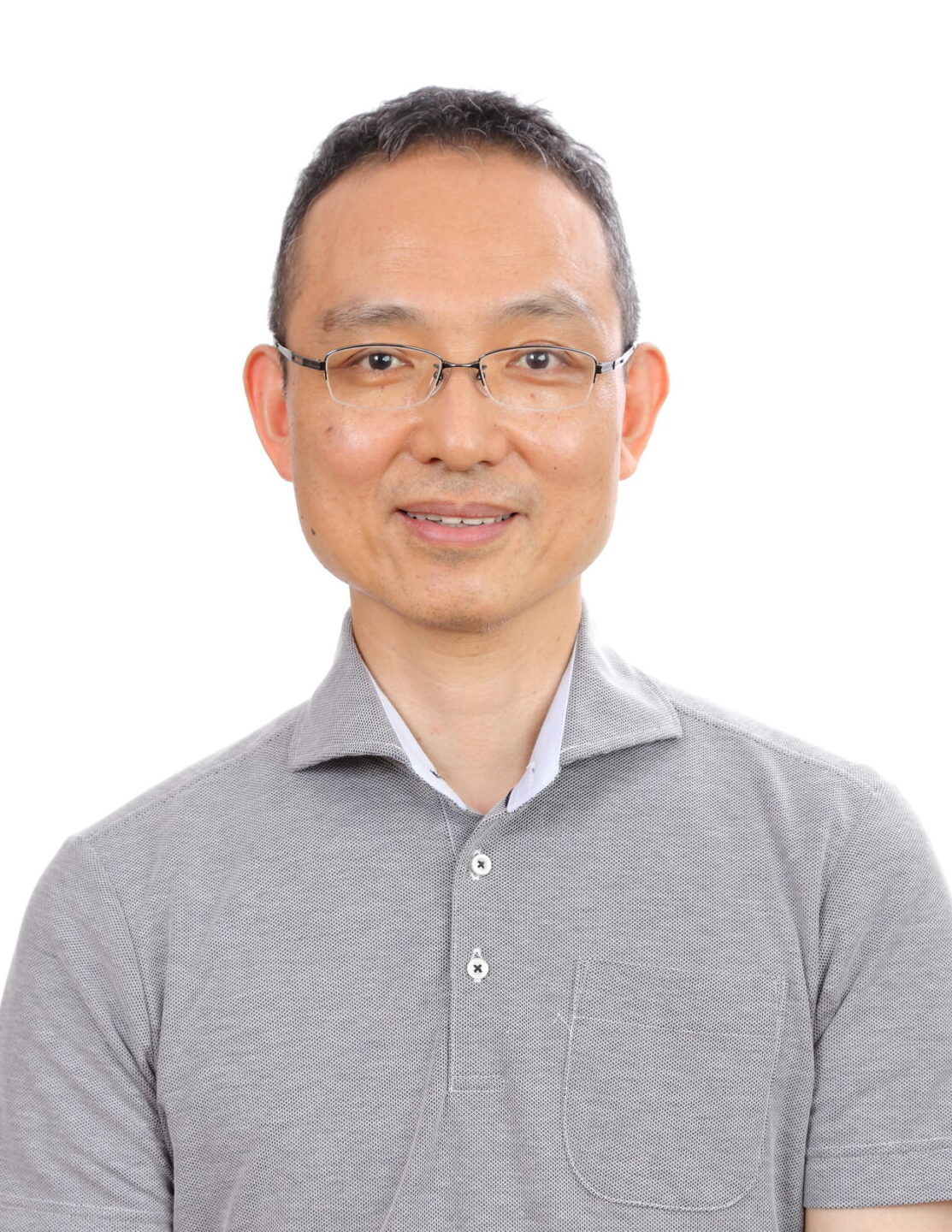[海外事例にみる継続支援アプローチ編]生成AIをヘルスケアサービスに活用する際のメリット
こんにちは、脇本和洋です。
本メルマガでは、海外のヘルスケアサービスの継続支援に関わる最新動向をチェックしています。
今回も2025年の注目動向である「生成AIの活用」についてお伝えします。
特集:海外事例にみる継続支援アプローチ編
2025年のヘルスケアビジネスを検討する上で注目となる「生成AIの活用」。
本編では、ヘルスケアサービスでの生成AI活用についてわかりやすくお伝えします。
前回までの2回にわたり、生成AIをヘルスケアサービスで活用する際によく聞かれる「課題」を6つに分けて紹介しました。
今回は、生成AIのヘルスケアサービス活用のイメージを膨らませていただくために、そのメリットをお伝えします。
※参考>本編のバックナンバー(2025年1月号、2月号):
生成AIをヘルスケアサービスに活用する時の課題
https://healthbizwatch.com/column/hbw-1118
https://healthbizwatch.com/column/hbw-1122
生成AIをヘルスケアサービスに活用するメリット
今回は代表的なメリットを3つ紹介します。
■メリット1:商品の購入継続率の向上
健康関連の商品の多くは継続して購入されることで収益があがります。
例えば、健康食品をイメージしてみましょう。
健康食品の継続率向上には「実感」が重要です。
実感を高めるには、商品以外の行動を取り入れてもらうことが大切で、多くの企業は会報誌やSNSなどで健康情報を提供しています。
しかし、その情報は一般的なもので、顧客ごとにパーソナライズすることは難しいです。
また、専門家サービスを導入してパーソナライズ化を図ると、高コストでスケールが難しいという課題がありました。
この課題に生成AIが役立つのです。
生成AIを活用すれば、短時間で顧客に合ったパーソナライズされた健康行動を提示できます。
「商品の購入継続率の向上のために生成AIが使える」。
これは1つ目のメリットです。
■メリット2:専門家が短時間でパーソナルな指導を行える
日本には数多くの健康専門家の方がおられます。
例えば、特定保健指導を行う方、フィットネスクラブで運動や栄養指導を行う方、整形外科でリハビリ指導をする方などです。
広い意味で言えば、健康食品の通販のコールセンターで簡単な健康アドバイスをするオペレータの方も含まれます。
運動や栄養について指導する際、「自宅でどのようなことを行うか」を伝える場面が出てきます。
多くの場合、限られた時間内でアドバイスする必要があり、一般的な情報を渡すのが精一杯となります。
ここで生成AIを活用すれば、短時間でその人に合ったパーソナライズされた在宅活動のアイデアを出せます。
このアイデアを参考にしつつ、専門家が顧客と話していけるようになります。
「専門家が短時間でパーソナルな指導を行える」。
これが生成AI活用の2つ目のメリットです。
■メリット3:既存アプリでのフィードバックの強化
これは、すでに健康アプリを運営し、顧客データ(行動データ)に基づいてフィードバックを行っている企業向けの活用方法です。
フィードバックを的確にすることで、アプリの価値を高めることが常に求められます。
しかし、フィードバックのパターンには限界があり、ユーザーが飽きやすいという課題があります。
生成AIを使うことで、単に数値に対してフィードバックするだけでなく、例えば、ユーザーが個別に残した主観コメントを見て、生成AIがその場で共感コメントを作り出すことができるのです。
「フィードバックの質が向上し、ユーザーが飽きにくくなる」。
これが生成AI活用の3つ目のメリットです。
「ヘルスケアサービス×生成AI活用」の具体的事例を知るために
今号では、「そもそもヘルスケアサービスに生成AIを活用するとどんなメリットがあるのか?」というご質問を多くいただいたため、その視点で紹介しました。
生成AIの活用には、今回のような基本を押さえておく必要があります。
私たちは生成AIを活用したヘルスケアサービスの開発を行っています。
先月のヘルスケアIT2025では、「きっかけデザインAI for Biz」として発表も行いました。
このサービスの紹介動画では、「メリット1:商品の購入継続率の向上」にフォーカスして紹介しています。
↓↓↓
https://youtu.be/cGMEvxzed_0
この例も参考にして、生成AI活用のメリットの理解を深めてください!
※生成AIを活用したヘルスケアサービスに関する基本的な知見や経験を共有するセミナーを定期的に開催しています。追って本メルマガでもお伝えします!
健康ビジネスキーワード
「動く人は、伸びる人」
ウェルビーイングの高い人は、じっとしていない。
新しい環境に触れるために移動し、刺激を受けることで心身の活力をキープしている。
ビジネスの世界でもフットワークの軽い人ほど成果を上げ、周囲にポジティブな印象を与えることと無関係ではないと思う。
これは、行動が学びを生み、視野を広げるからだ。
特にヘルスケア&ウェルビーイング事業に携わる人こそ、この姿勢が求められる。
自ら動き、体験し、現場の声を聞くことで、本当に価値のあるサービスが生まれる。
机上の議論ではなく、リアルな体験から学ぶことが、未来のウェルビーイングを創る鍵となるのだ。
あなたの次の一歩は、どこへ向かうだろうか?
今週の注目記事クリップ
+++★注目記事クリップ★+++
[1]Opera、休憩リマインダーやサウンドスケープを備えたマインドフルネス重視のブラウザをリリース
https://mhealthwatch.jp/global/news20250305
『Opera Air』は、集中力を高めるための休憩リマインダー、呼吸法、サウンドスケープ、バイノーラルビートなどの機能を備え、精神的健康とマインドフルネスに重点を置いている。(2025/03/05)
[2]パラマウントベッド、女性の眠りをサポートする「90日 わたしをみつめるねむりDIARY」誕生!
https://www.paramount.co.jp/news/detail/380
「90日 わたしをみつめるねむりDIARY」は、女性が眠りと生活習慣の改善に取り組むことにより体調を整えて健やかな日々を過ごすという目標に伴走するものです。(2025/03/05)
[3]CureApp、治療アプリで新たに2製品が製造販売承認~減酒、小児ADHDもアプリで治療する時代へ~
https://cureapp.blogspot.com/2025/03/2-adhd.html
デジタルセラピューティクス(DTx)は、医薬品や医療機器に続く「第三の治療法」として注目されており、世界中で研究開発が進められています。(2025/03/06)
[4]ライオン、歯科衛生士が歯科受診後にオンラインでサポート!歯科医院を通じた口腔ケア習慣化サービス『OraCo(オラコ)』を提供開始
https://www.lion.co.jp/ja/news/2025/4853
歯科衛生士がオンラインで一人一人の口腔ケア習慣化をサポートする新しい形のサービス提供により、予防歯科習慣の浸透を目指してまいります。(2025/03/06)
[5]Theoria technologies、脳の健康度セルフチェックツール「のうKNOW(R)」の個人向けサービス提供開始
https://theoriatec.com/news/20250306
「のうKNOW」は、トランプカードを使ったゲーム形式の4つのテストで脳の反応速度や注意力、視覚学習能力、記憶力といったブレインパフォーマンスを測定するセルフチェックツールです。(2025/03/06)
[6]Micoworks、クラシエの養生食サブスクEC「Fun to Me」が女性の健康と向き合うために、LINEを活用したパーソナライズコミュニケーションを実践
https://micoworks.jp/information/3787/
「Fun to Me」では、MicoCloud導入によりサブスク会員を対象にLINE公式アカウントでパーソナライズした健康アドバイスが受け取れるサービスを提供しているほか、更年期ケアのポータルサイト「Menotech Life」にて情報発信をおこない、更年期症状の市場理解を深める取り組みを進めています。(2025/03/06)
[7]スポーツテックのユーフォリア、住友生命と業務提携
https://eu-phoria.jp/news/pressrelease/20250306-sumitomo-seimei-partnership
本提携をもとに、ユーフォリアのスポーツ科学の知見と住友生命の保険・健康領域でのノウハウを組み合わせることで、新たな健康支援サービスの開発に向けて事業共創を推進し、より幅広い層の方々にスポーツの価値を届けてまいります。(2025/03/06)
[8]経済産業省、「健康経営優良法人2025」認定法人が決定しました
https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250310005/20250310005.html
「健康経営優良法人2025」として、日本健康会議により、大規模法人部門に3,400法人、中小規模法人部門に19,796法人が認定されました。昨年度の健康経営優良法人2024認定数に対し、両部門ともに大幅な増加が見られました。(2025/03/10)
[9]厚生労働省、令和4年国民健康・栄養調査報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r4-houkoku_00001.html
この調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき,国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とする。(2025/03/10)
[10]『mHealth Watch』注目ニュース:AIとLINEで、継続できるヘルスケアサービス『MY TRAINER』
https://mhealthwatch.jp/japan/news20250317
今回取り上げたのは、AIとLINEで継続をサポートするヘルスケアサービスなのですが、私が特に注目したのは、AIのヘルスケア領域での活用、アプローチについてです。(2025/03/17)
[11]ウンログ、天藤製薬・医師と共同で便の質を起点に健康に貢献する“うんちテック機能”「便質改善サポートツール&観便検定」を開発、ウンログ内に実装(PR TIMESより)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000057086.html
日本最大級の観便・腸活サポートアプリを運営するウンログは、天藤製薬、および消化器内科医・石井洋介氏と共同で、医師からアドバイスがもらえる「便質改善サポートツール」、ゲーム感覚でうんちの知識を身につける「観便検定」を開発しました。(2025/03/18)