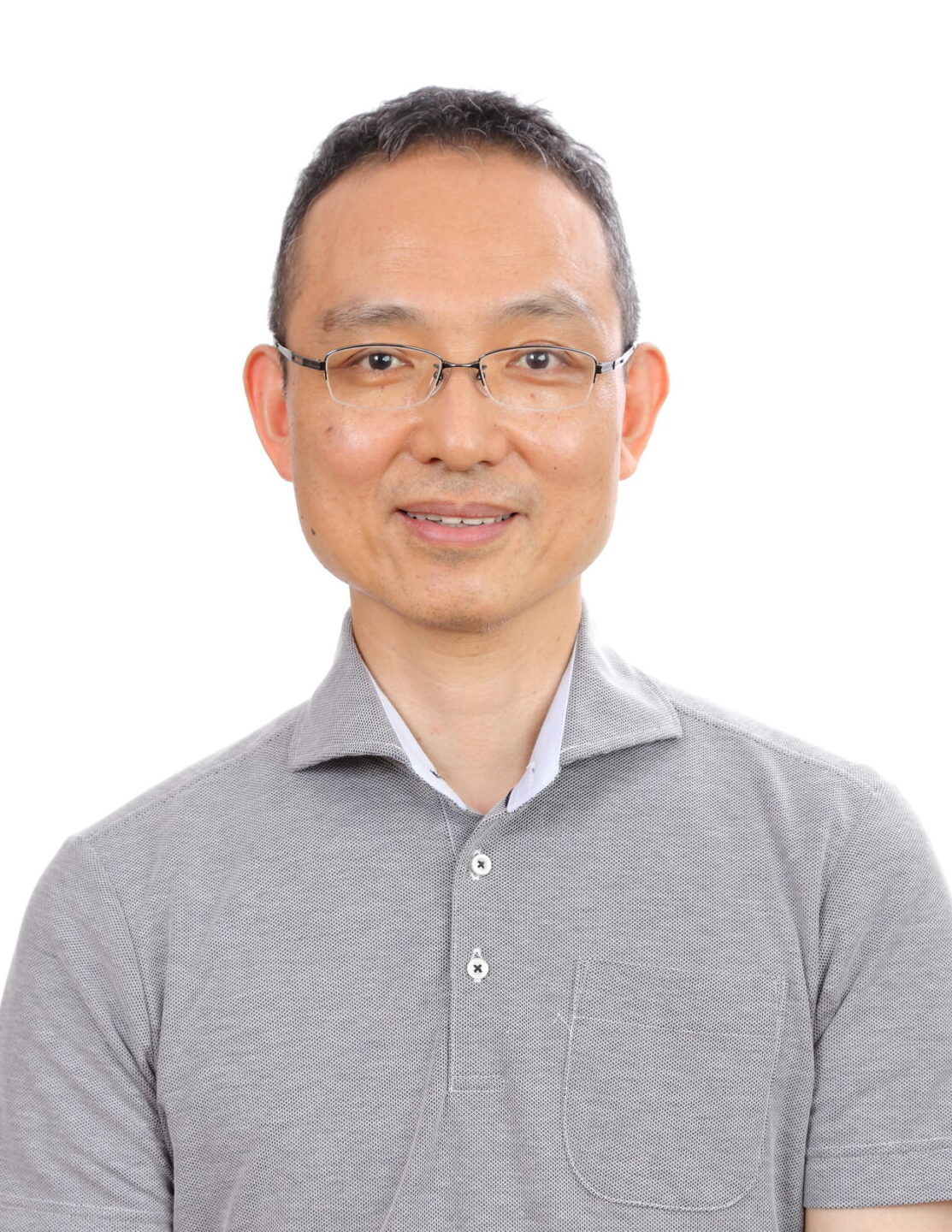[海外事例にみる継続支援アプローチ編]米国医療保険会社2社の健康サービス
こんにちは。脇本和洋です。
[海外事例にみる継続支援アプローチ編]では、健康サービスの継続利用を促す「基本」と、海外で注目したい「継続支援アプローチ」を紹介しています。今号は、米国の医療保険会社2社の健康サービスをみましょう。
特集:海外事例にみる継続支援アプローチ編
米国では公的医療は高齢者など一部に限られます。多くの人が自分の勤める会社を経由して、民間の保険会社の医療保険に加入しています。
ですので、医療保険会社は、医療費の抑制が経営課題となり、様々な健康サービスを継続して使ってもらい、少しでも病気にならないように(病気が進行しないように)注力します。
それだけに、「サービスの継続利用」いう視点でも、見どころも多い業界なのです。
米国の代表的な医療保険会社には、United Health/Independence Blue Cross/Kaiser Permanente/Anthem/Aetna/Humanaなどがあります。
今号では、これらの企業の中からUnited HealthとIndependence Blue Crossの健康サービスをみます。
(注:以下にて紹介する情報はオープンになっている範囲です。実際にはもっと多くの健康サービスを提供しています)
注目事例1:United Health
■医療保険会社名:United Health Group
https://www.unitedhealthgroup.com/
■健康予防サービスの概要
・HouseCallsとRallyという2つがサービスの基軸になる
・HouseCallsは、医者による無料の家庭内年次健康診断サービス。自社で提供
・Rallyは、健康増進支援サービスで、外部企業のものとなる
■注目サービスRally
https://www.rallyhealth.com/
Rallyは、以下のサービスを提供する。
・個人の健康状態に応じた予防サポートプログラム
・推奨される健康管理活動に連動するポイントプログラム
・ヘルスコーチによるサポート
・メンバーが他のメンバーと交流し、サポートするためのオンラインコミュニティ
サービスの特徴(継続の工夫)は、以下の3点をあげることができる。
・医療データや健康調査の結果を分析し、レコメンデーションエンジンが、個人のニーズに最も適したプログラムやアクティビティを推奨する(無理のない行動を推奨)
・またこの推奨されるプログラムやアクティビティにポイントを付与することで、ユーザーの行動を後押しする
・1対1のコーチングサービスで、参加者が健康的な習慣を身に付けるように促す。また、同様の課題を持つオンラインコミュニティに誘導し、相互のプレッシャーにより健康行動を促す
注目事例2:Independence Blue Cross
■医療保険会社名:Independence Blue Cross
https://www.ibx.com/
※Blue Crossは医療保険企業連合のこと。メンバー会社として、35の地域ベースの会社が存在
■健康サービスの概要
・Achieve well-being:動機づけするための仕組み(オンラインでの健康目標設定、アクションプラン設定、アクティビティトラッカーとの連動、モチベーション向上のためのトークン・バッジ付与 等)
・Health Coach:24時間365日利用できる看護師との健康相談
・Preventive Care:年次健康診断やワクチン接種などの予防ケア
・Nutrition counseling:年間6回の栄養カウンセラーとの対面での相談
・Discounts and reimbursements:以下についての割引やクーポン付与。健康器具、スポーツジム、健康関連プログラム、アミューズメント施設、ホテル、映画館 等
■注目サービスHealth Coaches
https://www.ibx.com/stay-healthy/health-and-wellness-perks/health-coaches
ヘルスコーチとして看護師がつく。以下のことを行う。
<健康づくりの理解促進>
・診断結果の理解を支援
・病気についての知識を提供
・健康管理をする方法を教える
<行動変容の促進>
・会員のHelath goalを明確にする
・Helath goalの実現にむけて寄り添う
・ライフスタイルを変えるための「選択支援」を行う(無理のない行動を支援)
健康づくりの理解促進だけでなく、ヘルスコーチが行動変容を促す点が特徴となる。
米国医療保険会社の健康サービスにみる継続支援
2つの事例のサービスの中で共通する点は何でしょうか。
・インセンティブ(ポイントがつく、スポーツジムなどの割引)がある
・ヘルスコーチングに力を入れている
ということが見えてきます。
前者のインセンティブは代表的な健康行動の継続手法ですが、
特に、注目したいのは後者の「ヘルスコーチング」です。
米国でも日本と同様、健康行動がいいことがわかっていても、なかなか続かない。そんな人が多いのです。
そのような人に対して、ヘルスコーチが、
・夢の持たせ
・無理のない健康行動を見つけさせ
・小さな変化に気づかせ、自信をもたせる
そんな要素を組み込んだコミュニケーションをしていきます。
そして、健康行動を他人事でなく、「自分事化」できるよう、支援するのです。
ヘルスコーチングという言葉というより、この要素にまず着目してみてください。 【脇本和洋】
参考>本編「海外事例にみる継続支援アプローチ編」をお読みの方へ
我々スポルツが今までに調べてきた500超の事例から実績をベースに16事例を選定。米国先進事例の「行動継続を促す工夫」を調査分析したレポートの紹介です。
詳細は以下となります。ぜひ参考にしてください。
●ヘルスビズウォッチ・レポート
継続ドライバ型海外先行デジタルヘルス事例16(2023年版)
ー サービスの継続利用を高めるアイデアを、
チームで精度高く短期間で生み出すための発想素材! ー
健康ビジネスキーワード
「顧客変化に素早く適応できる能力が今後のビジネス力」
コネクテッドの常態化と技術革新によって
創出された機会で生活者は
その行動・嗜好・期待・選択・消費が変化しています。
貴社の顧客は
貴社以外とも繋がっていて
顧客は貴社より速いスピードで進化しています。
顧客にとっての
新しい意味を絶えず共有することが
市場と顧客の変化を超えて生き残る術です。
今週の注目記事クリップ
[1]ヘルスケア業界の最先端プロモーションは映画級 事例5選(ウーマンズラボより)
https://womanslabo.com/category-marketing-case-210512-1
アニメ動画をプロモーションに活用している最新事例。特におすすめはSK-IIとイヴ・サンローラン。従来のブランディングを壊すことなく、見事に新たな世界観を創り上げている。(2021/05/12)
[2]ヤンセンファーマ、仕事と病の両立をさらに推進する「チームワークシックバランス」を発足
https://www.janssen.com/japan/press-release/20210513
「ワークシックバランス」とは、病を抱えながら働く人が周囲の理解を促しながら仕事と病との調和をとり、病があっても自分らしい働き方を選択できることを目指す考え方。(2021/05/13)
[3]トイレ排水から新型コロナの感染状況をモニタリング、集団感染を防止へ(日経デジタルヘルスより)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/10342/?ST=ch_digitalhealth
島津テクノリサーチは、高齢者施設や学校などのトイレ排水を解析して、新型コロナウイルスの感染状況をモニタリングする受託事業を開始。陽性反応があった場合は施設の利用者全体にPCR検査を促すことで、無症状者を含めた感染者を早期に特定し集団感染の防止につなげる。(2021/05/13)
[4]JTBと明治、腸の健康をテーマに中高生向け探究学習プログラム「おなかの学校」を共同開発、全国展開へ始動
https://press.jtbcorp.jp/jp/2021/05/jtb-2021.html
「おなかの学校」は、生徒自ら課題や疑問点を見つけ、それに対する答えを導き出す力をつける「探究学習」をベースに、「腸の健康」を学んでいくユニークなプログラム。(2021/05/14)
[5]ポッカサッポロフード&ビバレッジとサッポロホールディングス、ヤクルト本社との業務提携に関する協議開始
https://www.pokkasapporo-fb.jp/company/news/release/210514_01.html
ポッカサッポロおよびヤクルトは、相互が保有するリソースを活用し、事業の永続的な成長を実現することについて共通の認識を持つに至り、親会社であるサッポロホールディングスも含めた3社間において具体的な協議開始に合意。(2021/05/14)
[6]愛媛大学、世界初の研究成果!妊娠中の大豆、イソフラボン摂取が幼児の多動問題等に予防的論文発表
https://www.ehime-u.ac.jp/data_relese/data_relese-159404/
妊娠中の総大豆摂取が多いほど、5歳児における多動問題及び仲間関係問題のリスクが低下していた。大豆製品ごとの解析では、妊娠中の納豆摂取が多いほど、多動問題のリスクが低下した、など。(2021/05/14)
[7]広島大学など、イップスを発症しているアスリートでは運動時に特徴的な脳活動が見られることを解明
https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/64744
本研究では、イップスを発症しているアスリートにおいて同等の競技歴をもつアスリートと比較し、動作開始時にみられる事象関連脱同期(event-related desynchronization: ERD)と呼ばれる特徴的な脳波が増強していることを明らかにした。(2021/05/14)
[8]富士通と武田薬品、国立がん研究センターと卵巣がん患者さんのペイシェントジャーニーの分析・可視化に向けた共同研究を開始
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2021/05/17.html
本研究は、卵巣がんの個別化治療の質向上、および治療結果向上に寄与する臨床の課題抽出を目的として開始したもの。国立がん研究センター東病院及び先端医療開発センターにおいて2022年4月30日まで実施する。(2021/05/17)
[9]ユーグレナ、キューサイの連結子会社化のお知らせ
https://www.euglena.jp/news/20210517-2/
引き続きユーグレナ、APファンド、東京センチュリーの3者で密に連携しながら、キューサイのさらなる事業成長と「ウェルエイジング支援カンパニー」の実現に取り組んでいく。(2021/05/17)
[10]ライフコースとは?女性マーケティングの基本分類(ウーマンズラボより)
https://womanslabo.com/category-marketing-case-210517-1
ライフコースとは「個々の人生の道筋」という意味。人の人生は、就学、就業、結婚、出産、子の独立、家族の介護、家族との死別といった様々なライフイベントをきっかけに枝分かれてしていく。ライフコースはその道筋を線で捉えたもの。(2021/05/17)
[11]明治ホールディングス、グループスローガンを「健康にアイデアを」に刷新【PDF】
https://www.meiji.com/news/detail/pdf/2021/210518_01.pdf
https://www.meiji.com/
グループ内外の食と医薬の知見を融合させ、新しい価値を創造していき、特に「健康」というフィールドでこれまで以上に大きな役割を果たしていくことを目指す。(2021/05/18)
[12]DeSCヘルスケア、ヘルスケアエンターテインメントアプリ「kencom」を神奈川県鎌倉市に6月より提供開始
https://dena.com/jp/press/4737
本取り組みは、鎌倉市ICT活用健康づくり支援事業「古都をトコトコ鎌倉健康歩イント」の一環として行われる。歩数やアプリのログイン回数などに応じてポイントが貯まり、ギフトカード等の景品に交換ができる、など。(2021/05/18)
[13]Orchyd、スマートウォレットを備えた生理トラッカーを発表
https://mhealthwatch.jp/global/news20210512
フェムテック企業のOrchydは生理日管理アプリと、アプリに接続して使用し、1日分の生理用品を入れることができるスマートウォレットを発売する。(2021/05/12)
[14]音響機器のBoseが初の補聴器『SoundControl』発表、米FDAの承認取得
https://mhealthwatch.jp/global/news20210518
『SoundControl』はユーザー自身がスマホのアプリを使って聞こえを調整するという、これまでの概念を覆すものとなっている。FDAから医療機器としての承認を得ていて、ウェブサイトを通じて消費者に直接販売する。(2021/05/18)
[15]『mHealth Watch』注目ニュース:Mayo ClinicとKaiser Permanente、在宅重症ケアと回復サービスに投資へ
https://mhealthwatch.jp/global/news20210524
今まで病院で受けるのが当たり前だったことが、自宅でも提供可能になる。在宅診療の延長かもしれませんが、重症ケアなど、今まで考えもしなかった(考えないようにしていた)領域まで踏み込んできています。(2021/05/24)