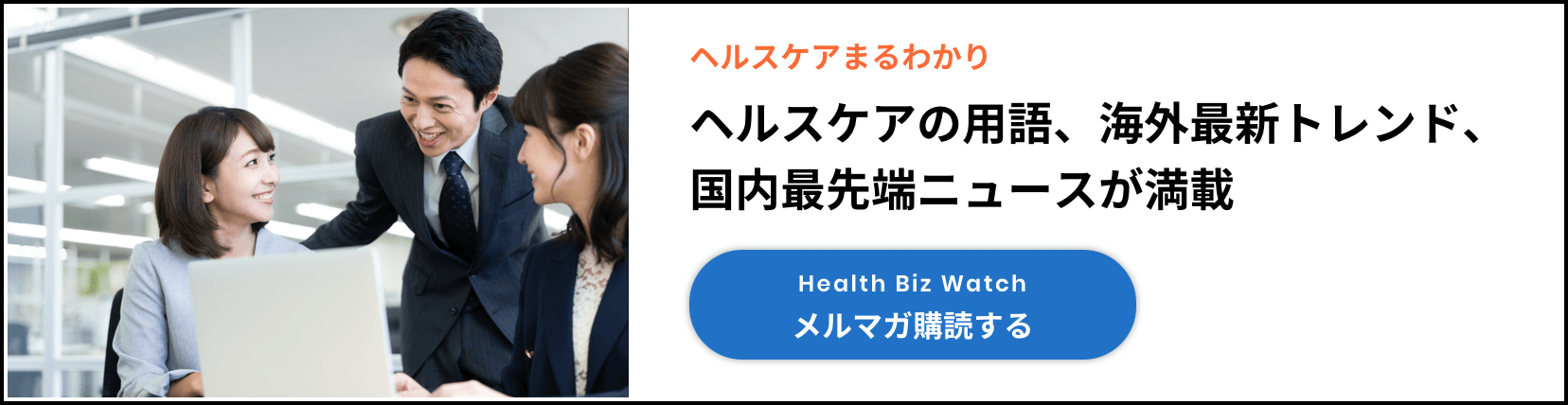ヘルスビズウォッチ視点で解説
2025年版 ヘルスケア用語解説
米国法人向けヘルスケアビジネスのトレンド
米国では1980年代頃から、ヘルスケアサービスは主に「Disease Management Program(重篤化予防)」と「Wellness Program(健康予防)」の2種類が用いられてきました。ところが近年、「Wellbeing Program」に置き換わってきています。
米国のコーポレートヘルス(日本の健康経営)は、主に医療保険負担を抑制することからはじまり、従業員のモチベーションアップ、生産性向上、業績改善など企業運営にとって望ましい効果が健康視点からも達成することを証明してきました。
その結果を見ていくと「健康になったこと」がそのまま業績改善につながるのではなく、「精神、肉体を含め健康を資本とした個々のウェルビーイング度が高まること」が企業にとって望ましい効果につながっていることがわかってきました。
そのため、精神的・肉体的健康にとどまらず、ウェルビーイングを高める「Wellbeing Program」が現在のトレンドとなっています。(2025年1月15日更新)
参考>米国法人向けヘルスケアビジネスマップ2024 詳細事例解説レポート―「売上好業績企業5社からわかる Wellbeing Programへ向かうニュートレンド」
米国法人向けヘルスケアビジネスの分類
米国法人向けヘルスケアビジネスの市場規模は3.5兆円(Fortune Business Insights 2023年調べ、1ドル150円換算)とされ、上昇傾向にあります。
提供企業は大きく5つに分類ができます。
1. 身体的健康サービス(食事、運動、生活習慣病予防などのサービスを提供)
2. 精神的健康サービス(うつ、不眠などの心の健康を意識したサービスを提供)
3. 社会的健康サービス(会社組織での健康、家族の健康を意識したサービスを提供)
4. 経済的健康サービス(金銭面での不安を減らし、安心して働けるサービスを提供)
5. 総合型健康サービス(経営戦略支援として、1~4のサービスを適時提供)
現在トレンドになっているのは総合型サービスで、そこでは身体的健康、精神的健康、社会的健康、経済的健康の複数を含む「Wellbeing Program」を提供している点が特長です。(2024年11月11日更新)
参考>「米国法人向けヘルスケアビジネスマップ2024」解説動画
ダイエット市場
ダイエット市場は、肥満、生活習慣病、お腹周りの脂肪、引き締めに関連する市場です。
令和元年国民健康・栄養調査報告によると、肥満者(BMIが25以上)は男性で33%、女性で22%ともなっています。また必ずしも肥満ではないが、お腹周りの脂肪が気になる人、つまり見た目を気にする人は数多く、お金を出しやすい健康テーマであることが特長です。
ダイエット市場には食品、医薬品、健康機器、アパレル、施設サービス、オンラインサービスなど様々な提供サービスがあり、その市場規模は、お腹周りの脂肪を意識した国内市場だけでも6,000億円程度(スポルツ調べ)とされ、大きな市場となっています。
我々HealthBizWatchの調査分析によると、ダイエット市場での成功事例は数多く、高収益化や継続利用率の向上の点でベンチマークの対象になっています。(2024年5月21日更新)
※厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」(2025年1月15日時点)
ヘルスケア市場
ヘルスケア市場は、医療(治療)領域と健康(予防)領域に大きく分けることができます。
HealthBizWatchは健康(予防)領域中心に最新動向を追っています。この健康(予防)領域の主なテーマには以下があります。
・ダイエット(肥満、生活習慣病、お腹周りの脂肪、引き締め)
・美容(ボディメイク、美肌、スキンケア、ヘアケア、姿勢など)
・エイジング(若々しさ、生涯歩行、転倒予防、聡明な脳など)
・疲労(だるさ、むくみ、休息、リカバリーなど)
・痛みの改善(腰痛・肩こり・関節痛など)
・睡眠(快眠、不眠など)
・ストレス(メンタルヘルス)
・オーラルヘルス(歯周病予防)
・腸の健康(腸活)
・女性の健康(妊娠・出産、生理痛、冷え性、更年期障害、骨の元気など)
・アレルギー(花粉症、アトピー性皮膚炎など)
多くのテーマは、個人の生活習慣(食事・運動など)の改善によって、健康(予防)が促進されるよう設計されています。(2024年4月22日更新)
ヘルスリテラシー
日本ヘルスリテラシー学会では以下のように定義しています。
「ヘルスリテラシーとは、一般に健康に関連する情報を探し出し、理解して、意思決定に活用し、適切な健康行動につなげる能力のことをいいます(厳密な定義についてはいろいろ議論があります)。
ヘルスリテラシーは、医療者-患者コミュニケーション、マスコミ・インターネット等による健康医療のメディアコミュニケーション、ヘルスキャンペーン等をすすめるにあたって、常に考慮すべき重要な要素です。
ヘルスリテラシーの高い人は、適切な健康行動をとりやすく、その結果、疾病にかかりにくく、かかっても重症化しにくいことが知られています。ヘルスリテラシーを向上させることによる効果については、まだ研究が十分ではありませんが、健康の維持・疾病の予防につながることが期待されています。」
※日本ヘルスリテラシー学会(2025年1月15日時点)
そもそも「ヘルスリテラシー」の「リテラシー」の本来の意味は「知識を活用できる」といった「活用」まで含んでいます。この「活用できる」とは、知識を使って情報を正しく選択するところまでではなく、やはりその先の「健康行動」まで含んでいるのが「ヘルスリテラシー」の本来の意味だと我々HealthBizWatchは考えています。(2024年3月12日更新)
行動変容ステージモデル
行動変容ステージモデルとは、1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルですが、その後食事や運動をはじめ、いろいろな健康に関する行動について幅広く研究と実践が進められています。
行動変容ステージモデルでは、人が行動(生活習慣)を変える場合は、「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通ると考えます。
運動にあてはめた場合のポイントは以下のとおり。
1. 無関心期への働きかけ:意識の高揚、このままでは「まずい」と思う
2. 関心期への働きかけ:身体活動が不足している自分をネガティブに、身体活動を行っている自分をポジティブにイメージする
3. 準備期への働きかけ:身体活動をうまく行えるという自信を持ち、身体活動を始めることを周りの人に宣言する 4. 実行期と維持期への働きかけ:援助関係、周りからのサポートを活用する
※厚生労働省 e-ヘルスネット「行動変容ステージモデル」(2025年1月15日時点)
行動変容ステージは、自社の想定顧客をイメージする際によく使われます。
想定した顧客に対してどんなサービスが響くか、それを検討する上で重要な切り口になります。(2024年2月13日更新)
データヘルス計画
「データヘルス計画は、国民の健康寿命の延伸を図るための新たな仕組みです。この計画が国民皆保険制度に導入されたのは、保険者がレセプト等の健康・医療情報を有していることや、加入者の疾病予防が医療資源の最適化に資するメリットがあることに加え、すべての国民をカバーし得る仕組みにできるからです。」
「データを活用して効果的・効率的にアプローチし、事業の実効性を高めていく。これがデータを活用した予防・健康づくりの特長です。データヘルス計画では、データに基づいて、これまでの取組みを客観的に振り返り、評価し、次の改善につなげます。」
※厚生労働省「データヘルス計画作成の手引き(第3期改訂版)」(2025年1月15日時点)
データヘルス計画は健康寿命の延伸を狙いとして、2015年に政府により策定されたものです。
わかりやすく言うと、健康保健組合(地方自治体)などが従業員(生活者)の健康データを収集分析し、的確な施策を打てるようにすることを指します。
2024年から第3期データヘルス計画が始まりますが、全体的には成果がどれだけ得られているかに重点を置く傾向があります。
また企業側(健康経営)との連携もより一層重視することとなります。
ヘルスケアサービス提供企業は、単にサービスを提供するだけでなく、従業員(生活者)が「健康行動を継続・定着させ成果に結び付けるサービス」へと進化させる必要があります。(2024年1月9日更新)
機能性表示食品と特定保健用食品
ヘルスケア業界の中でも大きな市場が食品領域です。
その中で機能性表示食品と特定保健用食品という2つの用語がよく出ます。その違いを捉えておきましょう。(2023年12月13日更新)
機能性表示食品
消費者庁では以下のように定義しています。
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです」
※消費者庁「『機能性表示食品』って何?」(2025年1月15日時点)
ポイントは、科学的根拠(文献調査でも可能)に基づいた機能性を、事業者の責任において表示できるという点です。
特定保健用食品
厚労省では以下のように定義しています。
「特定保健用食品は、身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取をするものに対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品。」
「食品を特定保健用食品として販売するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する国の審査を受け許可(承認)を得なければならない。」
※厚生労働省「『健康食品』について」(2025年1月15日時点)
ポイントは、臨床試験を行い、有効性を示し、国の審査を受け許可(承認)を得て表示できるという点です。
生活者に食品の効果をわかりやすく訴求できる点では、いずれの制度も素晴らしいですが、食品を摂取するだけで効果があるという誤解を招きやすいという課題も存在しています。
今後は、生活習慣を工夫して食品の効果を高めるヘルスケアサービスがセットで提供される時代になると予測しています。
デジタルヘルス
デジタルヘルスとは、情報通信・デジタル技術を活用したヘルスケア・サービスのことで、治療・回復、健康維持・増進、予防などの全て又は一部でデジタルを活用しています。
デジタルヘルスのソリューション領域は、メディカル、ヘルス、ウェルビーイングとフォロー範囲が広がっていき、介護もここに加わり盛り上がり始めています。(2023年6月8日更新)
デジタルヘルスの領域
人の健康状態が起点となる生活ビジネスを成立させるのがデジタルヘルス領域の技術であり、その日進月歩に注目が集まっています。
デジタルヘルスの技術とは、人工知能(AI)・チャットボット・IoT、ウェアラブルデバイス・仮想現実(VR)・ビッグデータ解析などを活用したものです。
例えばスマートウォッチ(ウェアラブルデバイス)で毎日の身体活動データをセンサーで取得し記録し分析し、自分のコンディションを管理し、また自身の目標に向かった行動選択に活用するという生活アクティビティはすでに現実のものとなっています。
スマートウォッチがセンシングするデータ対象が日頃の健康維持増進領域であったものが、今後疾患予防(未病・予防段階の介入)に活用でき、さらに疾病管理(治療効果や病態モニタリング)にパーソナルヘルスレコード(PHR)が使われるなどが現実化が進んでいます。
日経BPによる「デジタルヘルス未来戦略」公式ページから、7つの注目デジタルヘルス技術領域を引用します。
【7つの注目デジタルヘルス技術領域】
(1)健康管理支援
(2)モニタリングシステム
(3)データ管理・分析
(4)センサー
(5)バイオ技術支援
(6)画像診断
(7)医療機器・ロボット構造
※日経BP「デジタルヘルス未来戦略」(2025年1月15日時点)
スマートウォッチ(デバイス)&スマートフォンでは(5)(7)以外の全ての技術が集結して進化していく領域であることがわかると思います。
健康維持増進や予防観点でウェルビーイングへ拡張していくヘルスケアビジネスの中核を担っていくのがデジタルヘルスであると我々は考えております。
「デジタルヘルスはウェルビーイングと融合して生活アイテムになっていく」と仮説しています。
我々HealthBizWatchとしてもデジタルヘルス領域のプロジェクトサポートは80%を超えてきました。きっと全世界のヘルスケアはデジタルヘルスが牽引していくと思われます。
パーソナルヘルスレコード(PHR)
PHRは、Personal Health Recordの略で、直訳すると「個人の健康情報」ということになります。
ヘルスケアビジネスを検討する際には、様々な環境変化のキーワードに着目することが必要になります。その一つとしてPHRを捉えておきましょう。
まず海外の定義をみてから、国内の定義を整理します。(2023年6月8日更新)
PHRの定義(米国)
米国で医療情報管理に関して権威ある団体であるAHIMA(The American Health Information Management Association)は、PHRを以下のように定義しています。
「The personal health record (PHR) is an electronic, lifelong resource of health information needed by individuals to make health decisions.」
(訳)PHRは、個人が健康上の意思決定を行うために必要な健康情報の電子的で生涯にわたるリソースである。
※AHIMAによるPHRの定義(2024年1月9日時点)
ポイントは「健康上の意思決定を行うための情報」ということ。単に記録を眺めて終わりというのではダメで、その情報をみて何らかの決定や行動に結び付くということが大切なのです。
PHRの定義(国内)
まず、厚労省による定義をみましょう。
「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」によると、
PHRは
「個人の健康診断結果、服薬履歴、日常生活データ等の保健医療情報を、電子記録として正確に把握・活用するための仕組み」
と記述されています。
※厚生労働省「国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項(案)」 (2025年1月15日時点)
次に、PHR事業協議会による定義もみましょう。
PHRは
「生涯にわたる個人の保健医療情報 (健診(検診)情報、予防接種歴、薬剤情報、検査結果等診療関連情報及び個人が自ら日々測定するバイタル等)」
と記述されています。
※PHR事業協議会「団体設立ステートメント」 (2025年1月15日時点)
日本ではPHRは生涯における健康情報ということで、「情報そのもの」を指して使われる場合が多いのですが、米国では単なる健康情報というのではなく『情報をどう生かすか』という観点を重視した定義になっています。
我々HealthBizWatchは、米国での定義にある『情報をどう生かすか』を大切にしながらPHRの理解を深めることをお勧めします。
ヘルスビズウォッチとは(Chat GPTによる回答)
私が持つ情報によると、HealthBizWatchは、健康産業に関するニュースや情報を提供する、オンラインのニュースメディアです。
健康関連のビジネスに興味のある読者に向けて、医薬品、バイオテクノロジー、医療機器、ヘルスケアサービスなどの分野で、最新のニュースや業界トレンド、企業動向などを報じています。
HealthBizWatchは、健康ビジネスに関心のあるビジネスパーソンや投資家、医療関係者、政策立案者、研究者などにとって有用な情報を提供しており、健康産業の成長に寄与することを目的としています。
また、医療や健康に関する重要な問題について、専門家のコメントや解説も掲載しています。
上記の内容はChatGPTにヘルスビズウォッチについて問いかけたものになります。
的確に捉えていただいたと思いますが、いかがでしょうか?(2023年6月8日更新)
ヘルスケアとは(メディカルとの違い)
ヘルスケアとは直訳するとヘルス=健康とケア=管理で健康管理になります。メディカルは医療のことです。
ヘルスケアとメディカルには共通領域があります。
ヘルスケアはカバー範囲が広い言葉なので、全体像を理解する必要があります。
どの領域からフォーカスするかによって価値基準が異なる場合があります。(2023年2月24日更新)
「健康」の定義
まずはヘルスケアの基盤となる健康の定義を整理しておきます。
健康に関してWHOが定義する「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます」が有名です。
※公益社団法人日本WHO協会「世界保健機関(WHO)憲章とは」(2025年1月15日時点)
もう一度言いますが、ヘルスケアはとてもカバー範囲の広い言葉です。
公益財団法人日本ヘルスケア協会の2015年の定義によると
「ヘルスケアとは、自らの「生きる力」を引き上げ、病気や心身の不調からの「自由」を実現するために、各産業が横断的にそこの実現に向けて支援し、新しい価値を想像すること、またはそのための諸活動」とあります。
※公益財団法人日本ヘルスケア協会「ヘルスケアの定義」 (2025年1月15日時点)
この表現の中にある「病気や心身の不調からの自由を実現」はメディカルの範囲であることからヘルスケアはメディカルも含めた「生きる力」を引き上げるケアであると我々HealthBizWatchは解釈しています。
2つのヘルスケア
ここで注意したいのは“メディカル領域にポジションしたヘルスケアと、メディカル外のヘルスケア”が存在することです。
最近注目を集めているヘルスTECHのスタートアップのテーマはほとんどがメディカル領域におけるイノベーションをテーマにしています。
それに対して予防領域でのダイエットケアもヘルスケアといえるのです。
ヘルスケアとは医療内外の2つあるといえます。
ウェルネスとウェルビーイング
ウェルネスとウェルビーイングは、近未来におけるあらゆるビジネスや生活局面における重要キーワード&コンセプトであることは間違いありません。
この2つの違いよりも関連性を理解することが重要だと考えますので、各々の定義から確認していきましょう。(2023年2月24日更新)
ウェルネスとは
「ウェルネスとは、病気ではない状態であるヘルス(健康)を[基盤]として、その基盤をもとに豊かな人生、輝く人生を実現することが[ゴール]である。
何かに没頭している、熱中している、生き甲斐を見つけているなど、目指す過程も活き活きと輝いていればウェルネスであることが新しいウェルネス観として提唱されている」(ウィキペディアより)
※ウィキペディア「ウエルネス」 (2025年1月15日時点)
ウェルビーイングとは
「ウェルビーイングとは、誰かにとって本質的に価値のある状態、つまり、ある人にとってのウェルビーイングとは、その人にとって究極的に善い状態、その人の自己利益にかなうものを実現した状態である」(ウィキペディアより)
※ウィキペディア「ウェルビーイング」 (2025年1月15日時点)
HealthBizWatchにおける解釈は、ウェルネスは健康的コンディションが基本で、ウェルビーイングは幸福な状態、充実した状態など生活の質(QOL)の要素が占める比率が高いと考えられます。
ウェルネスは日本では2010年頃から使われており、使用頻度も時系列的に増加してきていましたが、2020年を過ぎ、ウェルビーイングがそれを上回る露出頻度になってきていると実感しています。その傾向を受けてか日本経済新聞は「2022年はウェルビーイング元年」といっているようです。
ヘルスケアビジネス(ヘルスケア事業)
ヘルスケア(健康管理)をビジネスとして行うことを意味するのがヘルスケアビジネスです。それは健康管理のモノ・コト・情報を提供することなのですが、誰が対価を支払うのかによってビジネスモデルが異なります。(2023年2月24日更新)
ビジネスモデルの違い
ケア対象者の健康状態によって健康管理の意味合いが異なることを注意しなければいけません。
治療・回復・健康維持は医療費(保険)領域になり、健康維持・増進・予防は医療費外となるのが一般的な捉え方になります。
いい換えると、ケアを始める時点の対象者の状態と目指す方向によってビジネスモデルが異なることを理解してください。
ビジネスと捉えた場合ヘルスケア領域に存在しているパターン
a) 患者に対応する病院やクリニックなどの医療機関を対象としたビジネス
b) 自治体や組織の構成員(市民または従業員)をケアするビジネス
※医療機関を営むことはメディカルビジネスになります。
ここまでが保険や組織の福利厚生などで大半のコストが賄われるケースとなります。
そして、受益者負担が基本であるビジネスが以下です。
c) 保険外の治療・回復系サービスビジネス
d) 健康維持・増進サービス及び物販
ヘルスケア事業参入に関する企業意識調査(PwCコンサルティング合同会社実施)の企業からの回答内容がとても注目に値すると思われるので抜粋します。
100億以上の企業で新規事業に携わる350人のマネジャー職へのウェブアンケート
1) 回答企業の約70%がヘルスケア事業への参入に積極的であり、約25%の企業が実際に事業を開始している
2) 回答企業の30%以上が「健康増進デバイス・アプリケーション」「健康経営」といった、既存事業から間口を広げやすいテーマに関心を寄せている一方で、「遠隔医療」「パーソナライズ医療」のような、治療領域への参入に興味を持つ企業は10%前後にとどまっている
3) 約半数の企業が「市場の成長性」「市場規模」といった、ヘルスケア市場のポテンシャルに期待を寄せているが、「ブランドイメージの向上」「顧客基盤拡大」といった具体的な事業への貢献を期待する企業は20%以下にとどまっている
4) ヘルスケア市場への参入に不安を感じている要因として、「ケイパビリティ・人材不足」「実行計画の不在」「ビジョン・戦略の不在」などを挙げた企業がそれぞれ約40%を占めている
まとめると多くの企業がヘルスケア市場に何らかの興味を持っているが、参入する決め手に欠いているといえないでしょうか。
そのような企業にこそHealthBizWatchは購読していただきたいのです。
※PwCコンサルティング合同会社「ヘルスケア事業参入に関する企業意識調査」 (2025年1月15日時点)